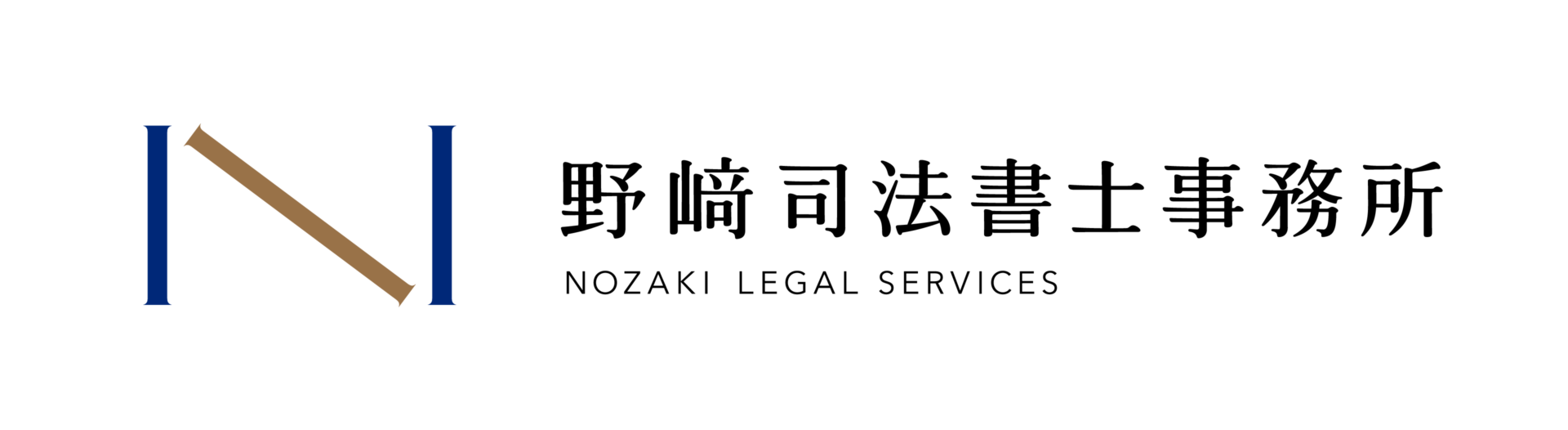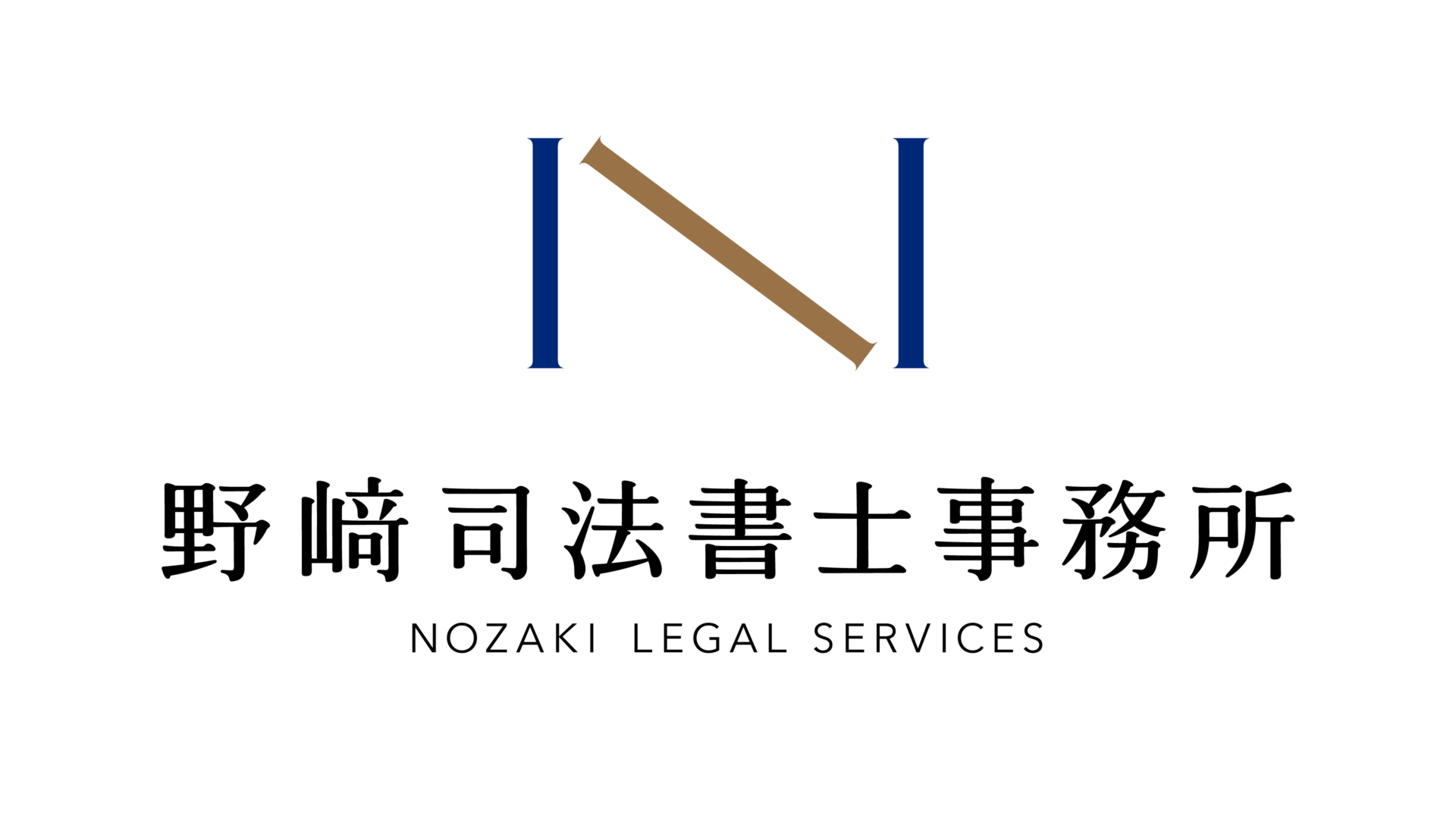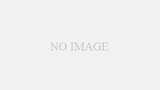はじめに
故人の遺言書を持参して「相続手続を進めてほしい」と相談に来られる方は、珍しくありません。
もちろん、遺言書が有効なものであれば、その内容に基づいて手続を進めていきます。
ただし、その遺言書が公正証書遺言でない場合には、通常、相続手続を始める前に「検認」の手続が必要になります。【1】
この手続の概要を事前に知っておくことで、相続人にとっては、あらかじめ対応方針を検討しておくことができます。
また、遺言書の作成を検討している方にとっては、どの方式で作成するのかを考える材料になると思われます。
以下、遺言書の検認について簡潔に解説していきます。
なお、相続手続の全体像については、こちらをご参照ください。
自筆証書遺言については、こちらをご参照ください。
公正証書遺言については、こちらをご参照ください。
また、相続手続のサポート内容については、こちらをご参照ください。
遺言作成のサポート内容につきましては、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
【1】自筆証書遺言保管制度を利用している場合も検認は不要
検認の概要
検認の手続については、遺言と同様に、民法によりルールが定められています。
まずは条文を確認してみましょう。
遺言書の検認
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
第1項にあるとおり、検認は、家庭裁判所に申し立てることによって手続を進めていきます。
申立人は、①遺言書の保管者、②保管者がいない場合には相続人、のいずれかになります。
もっとも、検認によって裁判所が遺言の有効性を判断するわけではありません。
検認とは、あくまで遺言書を現状のまま確認・記録することを目的とする手続なのです。
なお、上記の条文でも確認できるように、公正証書遺言については、検認は不要とされています。
法務局における自筆証書遺言保管制度を利用した場合にも、同様に検認は不要です。
また、1005条の規定についても確認しておくべきです。
封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料の対象となります。
遺言書を発見した場合、すぐにでも内容を確認したくなるのが人情というものですが、そこをぐっと堪えて、未開封のまま裁判所へ提出しましょう。
手続の流れ
検認の手続の流れは、以下のとおりです。
(1)申立て
・管轄の家庭裁判所(遺言者の最後の住所地)を確認
・必要書類の収集
・申立書類一式を裁判所に提出
(2)期日指定
・裁判所から検認期日が指定され、相続人全員に通知
・相続人は出欠を回答(検認は全員参加でなくてもよい)
(3)検認期日
・遺言書の原本、申立人の印鑑を持参
・遺言書が封印されている場合、裁判官が開封
・裁判官が遺言書を検認
・遺言書は原本を申立人へ返却
(4)検認後
・検認済証明書の発行を裁判所に申請
・検認済証明書と遺言書を使用し、相続手続を進める
以上です。
なお、手続完了までに要する期間は、裁判所の混雑状況に左右されるため一概にはいえませんが、1〜2か月程度を目安とされることが多いのではないでしょうか。
相続手続を急ぎたいからといって、検認の手続を省略することはできないため、この期間を考慮して方針を検討しておく必要があります。
遺言作成者の方にとっては、このことが、公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度の利用を検討する理由の一つになるといえます。
必要書類
検認申立に必要な書類は以下のとおりです。
・申立書
・遺言書の原本
・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・その他、裁判所から求められた書類
・収入印紙と郵便切手
相続関係が複雑な場合には、戸籍の収集に長い期間を要することがあります。
検認手続の期間もあわせると、相続開始までに数か月かかることも珍しくありません。
そのため、いざというときになって困ることがないよう、ご自身の置かれた状況を確認し、あらかじめ対応方針を検討しておくことが大切になります。
なお、相続人の調査・確定については、こちらをご参照ください。
司法書士に依頼するメリット
遺言書の検認が必要になる場面として典型的なのは、なんといっても不動産の名義変更手続(相続登記)です。
検認が不要とされている場合を除いて、検認をせずに相続登記を完了させることはできません。
そして、相続登記については司法書士が唯一の専門家です。相続登記を司法書士に依頼する場合には、検認もセットで依頼したほうが円滑に手続が進みます。
上述したように、戸籍収集や検認の手続には相応の期間を要します。
相続手続を少しでも早く進めたい場合には、遺言書の検認から相続登記までを一貫してサポートできる司法書士に依頼することをお勧めします。
まとめ
遺言書の検認は、遺言の内容を確認・記録するための大切な手続です。
一方で、家庭裁判所への申立てや、検認期日の立会いなど、相続人にとって負担となるものである部分も否めません。
公正証書遺言の方式により遺言書が作成されていたり、自筆証書遺言であっても法務局による保管制度が利用されている場合には、このような負担を相続人にかけることなく、速やかに相続手続に着手することができます。
もちろん、検認を要しない分、これらの方式や制度には遺言者にとって負担となる部分もあるため、どちらが正しいというものでもありません。
これから遺言書を作成する方は、相続開始後に検認が必要になる場合があることを理解し、どの選択肢がご自身にとって最適なのかを、あらかじめ周りの方や専門家に相談するようにしましょう。
相続人の方も、検認に要する作業や期間のことを把握しておき、いざというときに慌てなくて済むように方針を検討しておきましょう。
当事務所では、円滑に相続手続を進められるよう、検認の手続をサポートいたします。
川越市周辺で司法書士をお探しの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。
なお、相続手続のサポート内容については、こちらをご参照ください。
遺言作成のサポート内容につきましては、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。