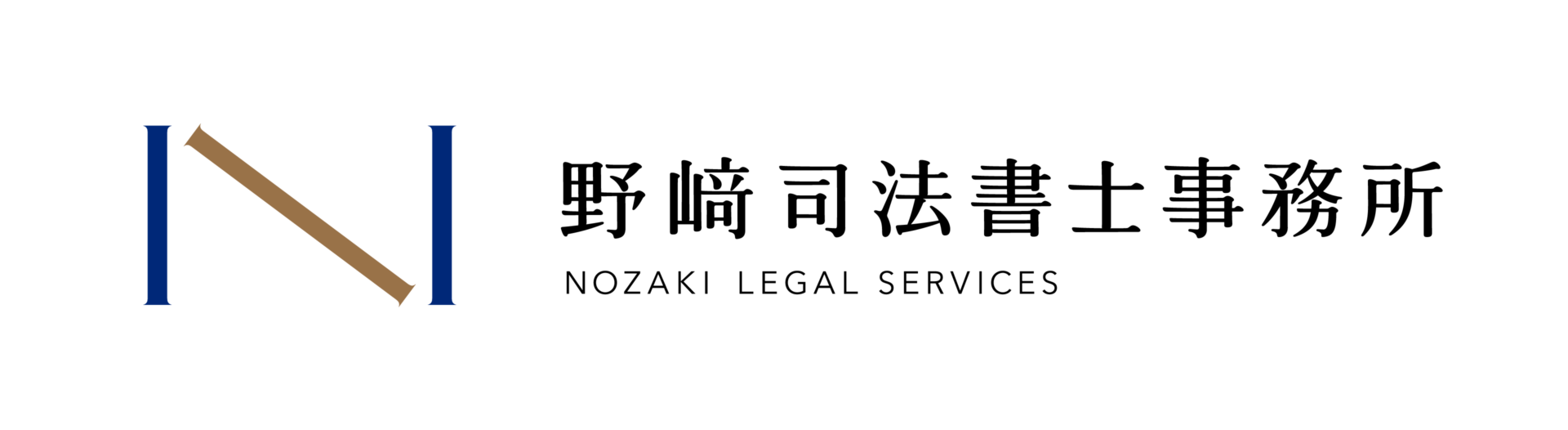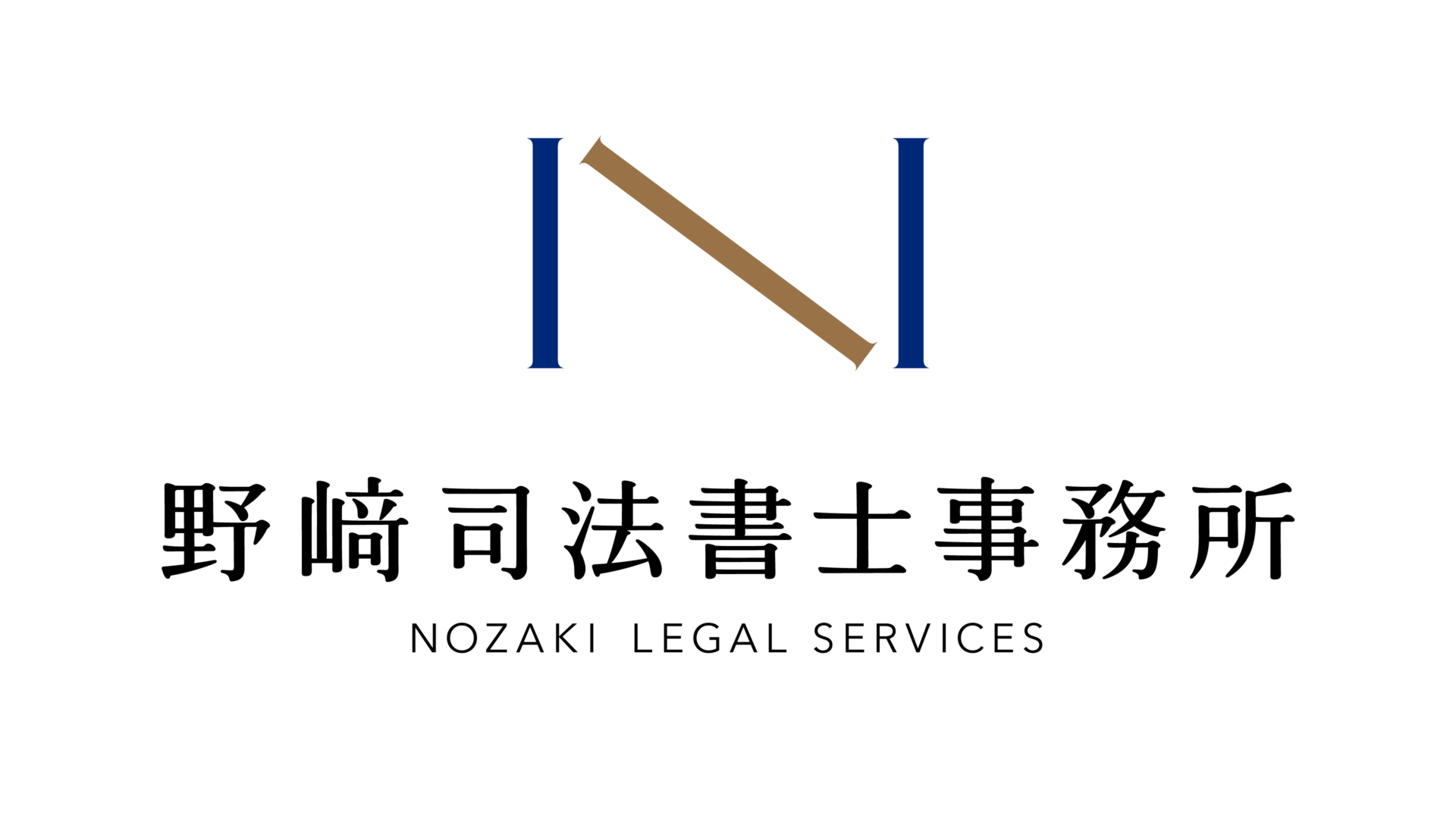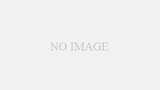はじめに
司法書士は相続手続の専門家ですが、将来の相続発生に備えたいという方に向けて、遺言作成のサポートも行っています。
あらかじめ遺言書を作成しておくことにより、相続手続が簡易・迅速に進みやすく、相続人間のトラブルも未然に防ぎやすくなるからです。
もっとも、遺言書は、作成すれば万事解決というものではありません。
遺言者の意思に沿って遺言の内容が実現されて、はじめてその役割を果たすことができるのです。
このように遺言の内容を実現していくことを、「遺言執行」といいます。
そして、遺言執行を進める人のことを、「遺言執行者」といいます。
遺言の内容を実現する上で、この遺言執行者の責任は非常に重大です。
以下、遺言執行者による遺言執行の概要や注意点などについて、簡潔に解説していきます。
相続手続の全体像については、こちらをご参照ください。
なお、相続手続のサポート内容については、こちらをご参照ください。
遺言作成のサポート内容につきましては、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続財産を管理・処分する権限を持つ人のことです。
まずは民法の条文で確認してみましょう。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
「遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とあるように、相続手続の場面において、遺言執行者のもつ権限は非常に強力です。
さらに、「遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」とあるので、たとえ相続人であっても、勝手に相続財産の処分をできない場合があることが分かります。
では、遺言の執行に必要な行為とは、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。
次項で確認していきましょう。
遺言執行者の主な役割
相続手続の中で遺言執行者が行うものは、多岐にわたります。
特に重要と思われるものを、以下に列挙します。
・不動産の相続登記の申請
・預貯金の解約・払戻し
・株式や投資信託の名義変更
・遺産の分配(遺言に基づいて振込みなどを行う)
・遺贈の実行(特定の人や団体に財産の権利を移転する)
・その他、認知や廃除などの身分行為
たとえば遺言の内容が「不動産は長男、預貯金は長女、株式は二女に相続させる」といった内容であった場合でも、遺言執行者が指定されていれば、その人に全ての手続を任せることができることになります。
繰り返しになりますが、遺言執行者の権限はそれだけ強力なのです。
そうすると、誰が遺言執行者に就任するのかということが重要になります。
次項では、遺言執行者の指定方法について解説します。
遺言執行者を指定する方法
遺言執行者の指定方法についても、まずは民法の条文を確認しましょう。
(遺言執行者の指定)
第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の選任)
第1006条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
基本的に、遺言執行者は遺言で指定することになります。
遺言の文中に「本遺言の遺言執行者として、〇〇を指定する」のように記載する方法が一般的です。
もっとも、遺言で遺言執行者が指定されている場合でも、その指定された人が必ず遺言執行者に就任するわけではありません。
遺言執行者は、多額の相続財産を取り扱うこともあるので、その責任は重大です。
そのため、遺言執行者への就任を辞退することも認められているのです。
このような理由によって遺言執行者がいない場合には、利害関係人が家庭裁判所に請求することで、家庭裁判所が選任する場合もあります。
遺言執行者になれる人
基本的には、遺言で指定されることで、誰でも遺言執行者になることができます。
ただし、民法上の欠格事由に該当すれば、この限りではありません。
条文を確認しましょう。
(遺言執行者の欠格事由)
第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
このように、未成年者と破産者については、相続財産を管理・処分する上で明らかに不適と考えられるため、遺言執行者になることはできません。
実務的には、相続手続に精通した司法書士などの専門家が選ばれることが多いかと思います。
近年では、銀行などの法人が指定されている場合もあります。
もちろん、相続人の一人を遺言執行者に指定することも可能です。
ただし、その場合には公平性をめぐって相続人間でトラブルになる可能性もあるため、遺言作成の段階から家族で話し合っておくなど、事前の準備が大切になります
遺言執行者の解任・辞任
ここまで見てきたように、遺言執行者は相続財産の管理・処分をする権利義務をもちます。
だからこそ、悲しいことですが、時には遺言執行者が相続財産を着服してしまう事件なども起きてしまうことがあります。
そこまでいかなくとも、なかなか相続手続を進めないなど、相続人などの利害関係人にとって不利益な事態を招くこともあり得ます。
そのような場合に備えて、民法上、次のような規定が用意されています。
(遺言執行者の解任及び辞任)
第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
このように、正当な事由がある場合には、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求することができます。
なお、遺言執行者には職務を全うする義務がありますが、何かの事情でそれが難しくなった場合になどには、家庭裁判所の許可を得ることで辞任することができます。
事情がある場合でも、許可なく勝手に辞任することはできないので、注意が必要です。
司法書士に依頼するメリット
司法書士は、相続手続全般に精通しています。
特に、相続による不動産の名義変更(相続登記)については、司法書士が唯一の専門家です。
また、将来の相続手続を見据えた遺言作成についても、専門家としてサポートを行うことができます。
このため、遺言作成時点で司法書士を遺言執行者として指定することで、生前対策から相続手続までをワンストップで任せることができます。
なお、相続手続の全体像については、こちらをご参照ください。
まとめ
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために欠かせない存在です。
遺言者にとって信頼できる人を指定することが基本ですが、相続手続の円滑な進行や相続人間のトラブル防止の観点からは、司法書士などの専門家に依頼するほうが安心といえます。
当事務所では、遺言内容に応じて適切に遺言執行が進められるよう、相続手続や遺言作成をサポートしております。
川越市周辺で司法書士をお探しの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。
相続手続のサポート内容については、こちらをご参照ください。
遺言作成のサポート内容につきましては、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。