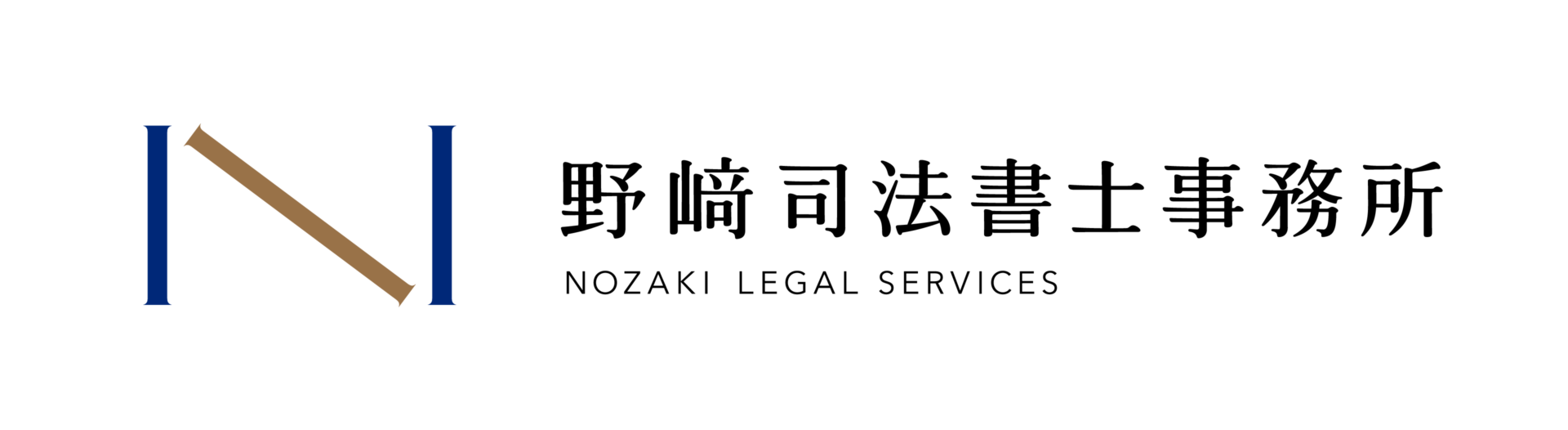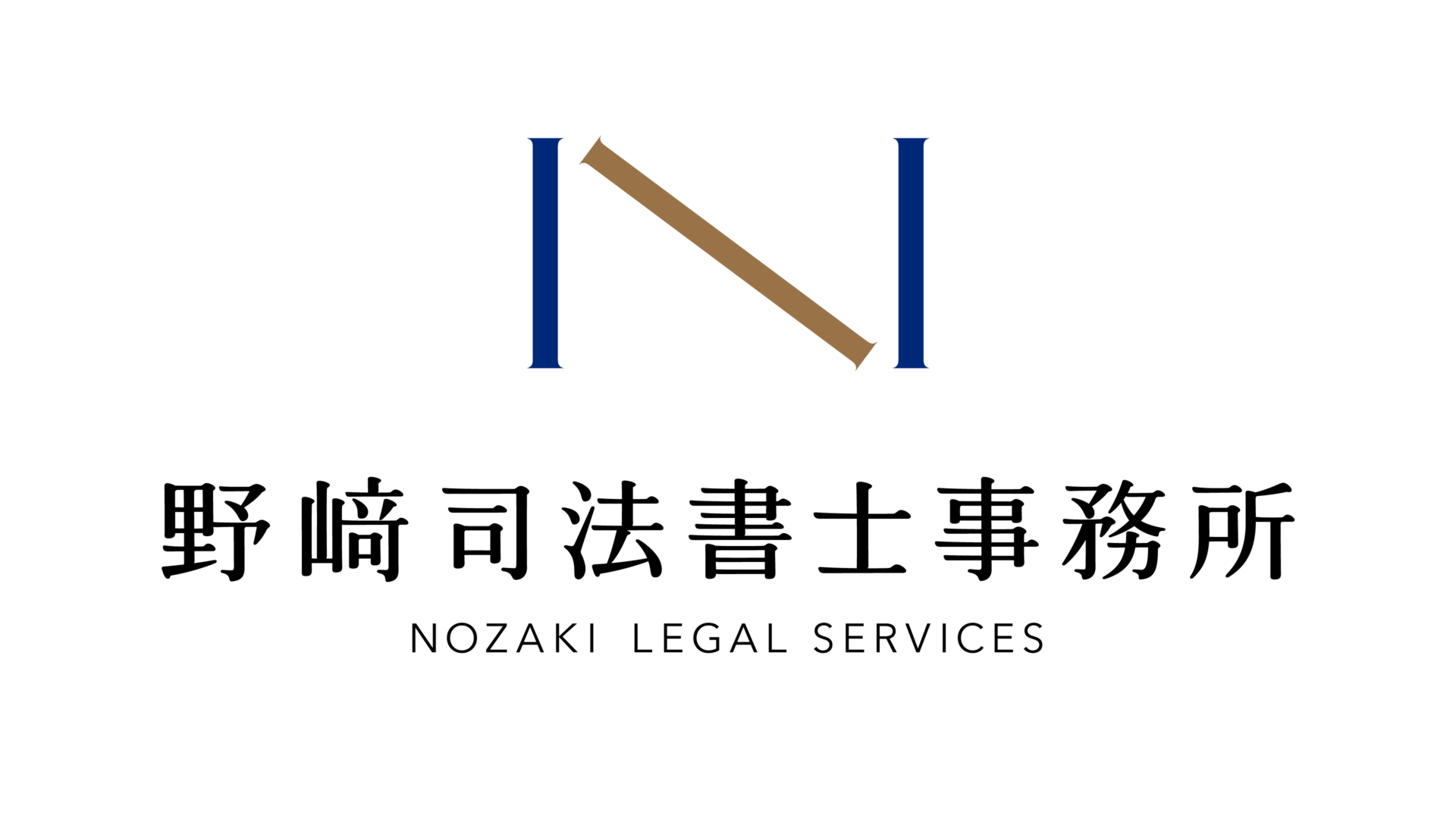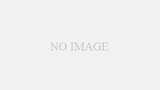はじめに
相続手続を円滑に進める上で大きな役割を果たすのが、遺言です。
相続人が多数いる場合や、相続人間が疎遠な場合など、遺産分割協議が成立しにくいときでも、遺言書を利用することにより、相続財産を分配しやすくなります。
遺言を作成すること自体は、それほど難しいことではありません。
自筆証書遺言の方式であれば、紙とペンと印鑑さえあれば、いつでもどこでも作成することができます。
一方で、遺言のもつ法的効力は、とても影響力が大きいものです。
そのため、作成する際は、慎重に内容を検討するべきといえます。
また、せっかく作成した遺言書が無効になっては、元も子もありません。
遺言者の意思を確実に実現するためには、形式面や文言、保管方法や執行の流れなどを、しっかりと確認しておく必要があります。
安心して手続を進めるためには、遺言者も相続人も、あらかじめ遺言制度について理解を深めておくことが望ましいと考えます。
以下、遺言作成・執行の全体像について、解説していきます。
遺言作成のサポート内容については、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
遺言の概要
遺言とは、遺言する人(遺言者)の最終の意思表示のことをいいます。
遺言者の死亡(相続の開始)とともに効力が生じ、法的にとても大きな意味をもちます。
一般的に、相続財産(遺産)の分配方法について定めることが多いと考えられます。
通常、相続が開始すると、相続人同士の遺産分割協議によって、遺産の分け方を決めることになります。
一方で、遺言がある場合には、その内容によって財産の承継方法が決まります。
このとき、法定相続分どおりに遺産を分ける必要はありません。
たとえば、妻と子ども2名が相続人となる場合、その法定相続分は、妻が2分の1、子どもが各4分の1となります。
しかし、遺言を残しておくことによって、全財産を妻に相続させたり、相続人でない第三者に贈与したりすることも可能となるのです。
実務的には、遺産分割協議の成立が困難となることが予想される場合に、遺言作成を検討することも多いように感じます。
上記の例でいえば、子どものうち一人が音信不通となっていた場合には、協議をすること自体ができなくなります。そうすると、不動産や預貯金などの財産の相続手続が進められなくなり、生活に支障がでかねません。
一方で、遺言があれば、協議をすることなく相続手続を進めることができます。
この点が、遺言作成の大きなメリットの一つなのです。
ただし、遺言をもってしても相続人の遺留分を侵害することはできないため、注意が必要です。
また、遺言の方式は法律で厳格に定められており、方式に不備があると無効になるおそれがあります。
遺言にはいくつかの方式がありますが、そのうち代表的なものが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
次項以下に概要を記載しています。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆し、押印することで成立します。
遺言書のうち財産目録については、パソコンで作成したものや、証明書等を添付する方法も認められています。ただし、この場合でも財産目録の各ページへの署名・押印は必要です。
自宅でも手軽に作成でき、費用もほとんどかからないことが大きなメリットといえます。
一方で、第三者のチェックを経ずに作成できることから、形式の不備や紛失・改ざんのリスクが比較的高くなります。また、相続発生後に、家庭裁判所の検認が必要となる点には注意が必要です。
もっとも、後述する自筆証書遺言保管制度を活用した場合には、上記のデメリットの大部分をカバーすることができます。
より確実に遺言の内容を実現したい場合には、司法書士のサポートを受けることをお勧めいたします。
自筆証書遺言の作成については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
当事務所では、自筆証書遺言の作成のサポートも承っております。
詳しくは、こちらのサービス案内をご覧ください。
自筆証書遺言保管制度
この制度は、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けて保管してもらえるというものです。
主なメリットは、以下のとおりです。
・形式のチェックを法務局が行い、遺言書の要件不備のリスクを軽減
・原本と画像データを長期間保管してもらい、紛失や改ざんのリスクを軽減
・家庭裁判所での検認が不要となり、相続手続を円滑に進められる
・相続開始後すぐに閲覧可能(全国どの法務局からでもアクセス可能)
・相続人等への通知制度により、遺言書の存在を知らせることが可能
ただし、申請できるのは遺言者本人のみで、代理人による申請はできません。
また、遺言の内容に関する審査は行われないため、遺言者の意図に沿った内容かどうかをチェックしてもらうことはできません。
よって、この制度を利用する場合でも、司法書士などの専門家のサポートを受けることをお勧めいたします。
自筆証書遺言の保管制度については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
当事務所では、自筆証書遺言の作成のサポートも承っております。
詳しくは、こちらのサービス案内をご覧ください。
公正証書遺言の作成
最も信頼性の高い遺言として、実務上もお勧めされやすい方式です。
証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の意思を確認した上で作成します。
主なメリットは、以下のとおりです。
・形式の不備により無効となるリスクが極めて低い
・遺言者の意思能力が確認される
・遺言原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがない
・家庭裁判所での検認が不要で、遺言執行がスムーズ
・遺言者が手書き不可の状態でも作成が可能
ただし、この方式で作成するためには、公証役場に所定の手数料を支払わなければなりません。
また、遺言の内容が証人や公証人に知られてしまう点については留意する必要があります。
公正証書遺言の作成については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
当事務所では、公正証書遺言の作成のサポートも承っております。
詳しくは、こちらのサービス案内をご覧ください。
遺言の検認
公正証書遺言以外の遺言書を相続手続に利用するためには、原則として、家庭裁判所における検認の手続が必要です。
検認とは、相続人の立ち会いのもと、裁判所において遺言書の内容を確認する手続です。
これは遺言書の存在と内容の確認・記録を目的とするもので、遺言の有効性を判断するものではありません。
封印された遺言書を検認の前に開封すると、5万円以下の過料を科される場合があるため、注意が必要です。
遺言の検認については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
当事務所では、遺言の検認のサポートも承っております。
詳しくは、こちらのサービス案内をご覧ください。
遺言の執行
遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことです。
これを担う遺言執行者は、遺言により指定することができます。
遺言執行者は、相続登記や預貯金の解約・払戻しなどの手続を行う権限をもちます。
遺贈の実行など、遺言執行者にしかできない手続もあります。
その一方で、重い責任を負うことにもなりますので、遺言執行者の解任や辞任の手続も用意されています。
遺言の執行については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
当事務所では、遺言の執行のサポートも承っております。
詳しくは、こちらのサービス案内をご覧ください。
まとめ
遺言作成は、ご自身の財産の使い道を決められる、大切な機会です。
そして、作成したからには、その内容が確実に実現されるべきものです。
そのため、作成して終わりではなく、保管・検認・執行までを見据えて準備することが大切です。
専門家と相談しながら、ご自身に合った方法を検討されることをお勧めします。
より詳しい情報は、各記事にて解説しています。
必要に応じて、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
「そもそも、司法書士とはなんなのか?」というところから確認したいという方は、こちらをご参照ください。
当事務所では、遺言作成から遺言執行まで、相続に関する手続を一括でサポートしています。
また、生前対策における税計算など他士業のサポートが必要になる場合には、それぞれの専門家をご紹介いたします。
川越市周辺で司法書士をお探しの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。
遺言作成のサポート内容については、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。