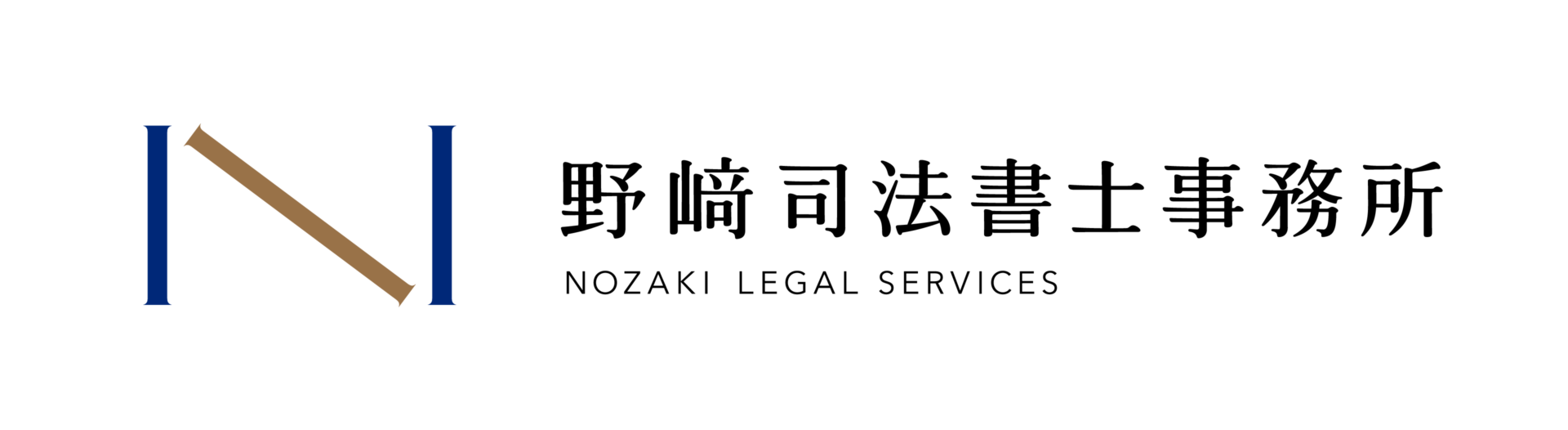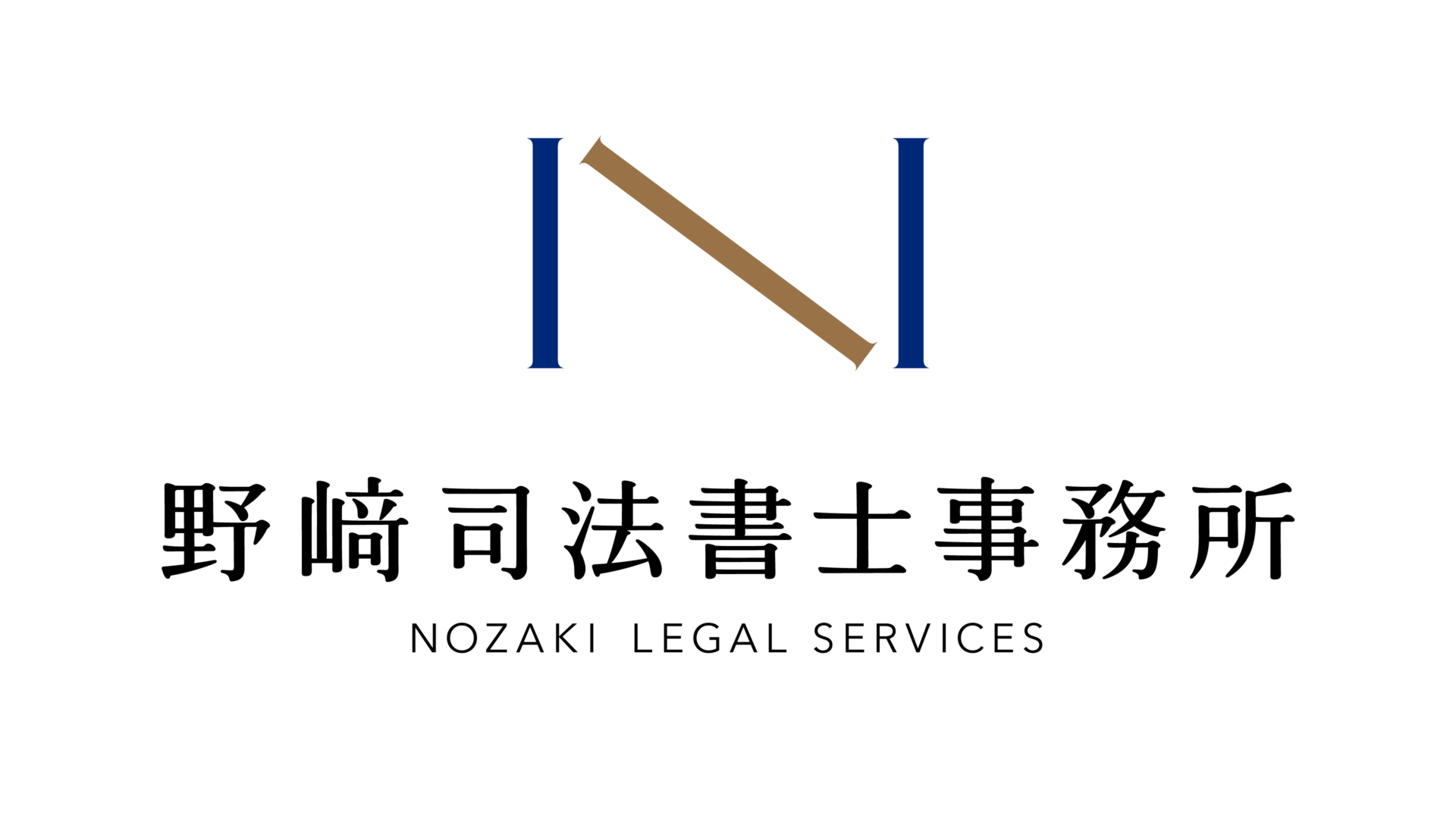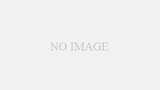はじめに
相続が発生した際、預貯金の解約・払戻しの手続は、相続人にとって大きな関心事になりやすいといえます。
自宅などの不動産を除けば、相続財産として最も高額になるのは、多くの場合、預貯金だからです。
また、亡くなった方(被相続人)の葬儀をはじめ、相続を契機とした出費が重なることも少なくありません。
場合によっては、相続財産となる預貯金を早急に口座から引き出したい、ということもあるでしょう。
このように被相続人の預貯金を引き出す際は、預貯金の解約・払戻しという手続を行うことになります。
一方で、預貯金を預かっている金融機関側からすると、無条件で解約・払戻しを認めるわけにはいきません。
解約・払戻しを請求してきた相手が、本当に預貯金を相続する権利を有しているのかを、しっかりと確認しなければならないからです。
この記事では、預貯金の解約・払戻しの流れについて、司法書士の視点から解説します。
なお、「相続財産の調査・確認」についても、並行して進めておくことをお勧めします。
詳細につきましては、こちらをご参照ください。
また、相続手続の全体像を確認したい場合には、こちらの記事をご参照ください。
口座の凍結
まず、預貯金の解約・払戻しを行う前に、口座の凍結を行うことになります。
凍結により、預貯金を口座から引き出したり、逆に口座に入金したりすることができなくなります。
被相続人(亡くなった方)が利用していた口座は、その方の死亡を金融機関が認識した時点で凍結されるのが一般的です。
「被相続人の死亡届を市役所などに提出することにより、自動的に口座が凍結されるのか?」
という質問をいただくことがありますが、行政手続と金融機関の口座が紐づいているわけではないため、本記事を執筆した令和7年時点では、自動的に凍結されることはありません。
基本的には、相続人から金融機関に相続発生の事実を連絡することにより、口座の凍結が行われるのが一般的です。
この連絡は、相続人から委任を受けた司法書士などが行うこともあります。
残高証明書の取得
口座が凍結されたあとは、準備が整い次第、解約・払戻しを請求することもできます。
もっとも、当事務所では、その前のステップとして、「残高証明書」を取得することをお勧めしています。
残高証明書とは、指定日時点での口座の残高を金融機関側に証明してもらうための書面です。
基本的には、死亡日時点の残高証明書を取得することが多いですが、必要に応じて直近の残高証明書を取得することもあります。
死亡日時点の残高証明書
被相続人の死亡日時点での預金残高が記載されます。
被相続人の相続財産(遺産)とは、被相続人が死亡した時点で所有していた一切の財産のことを指します。
このため、死亡日時点での預金残高がいくらなのかを把握することで、正確な相続財産の評価を行うことができます。
正確な相続財産を把握することは、次のような場面で特に必要となります。
◯遺産分割協議
相続人が複数いる場合に、それぞれが把握している財産額に差異があると、トラブルの原因になります。
◯遺留分算定
遺留分算定の基礎になるのは、相続発生時点での財産額であるため、死亡日時点での残高証明書に基づき正確に計算することが重要です。
◯相続税申告
相続税を計算する上でも、やはり死亡日時点での残高証明書が必須となります。
このように、相続手続を進める上で、死亡日時点の残高証明書を取得することは非常に重要といえます。
直近の残高証明書
被相続人の預金の動きを把握したい場合、直近の残高(凍結時の残高)を記載した証明書も取得することがあります。
死亡直前に大きな出金や振込がないかを確認する際に、役立つ書類となります。
残高証明書の取得に必要な書類
金融機関によって異なりますが、代表的なものは以下の書類です。
・被相続人の除籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄抄本
・相続人の本人確認書類
・銀行所定の請求書、委任状(代理人が請求する場合)など
実際に請求を行う際は、必ず金融機関ごとの必要書類を確認するようにしましょう。
解約・払戻し手続き
解約・払戻しの手続は、多くの場合、被相続人名義の口座から相続人名義の口座に預貯金を振り込む方法によって行われます。
その際、以下のいずれかの方法を選択することが一般的です。
代表者の口座にまとめて振り込む方法
相続人のうちの1人を「代表者」として指定し、その人の口座に全額を払い戻す方法です。
その後、代表者から他の相続人の口座へと預貯金を振り込むことが多いと思われます。
この方法は、実際に金融機関とやりとりをするのが代表者1名だけで済むため、手続が簡便に進められるというメリットがあります。
一方で、代表者が預貯金を着服しやすいなどのリスクもあるため、相続人間の信頼関係が重要といえます。
また、手続の際は、通常、金融機関から次のような書類の提出を求められます。
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
各相続人の口座に分割して振り込む方法
相続人それぞれの口座に、あらかじめ取り決めた金額を分割して払い戻す方法です。
通常、金融機関所定の書式に、払戻しを受ける相続人の署名・実印を求められます。
また、払戻しを受ける相続人の口座情報も提供する必要があります。
解約・払戻しに必要な書類
いずれの方法の場合でも、通常、金融機関から以下の書類の提出を求められます。
別途、遺産分割協議書等が必要になることがあるのは、上述したとおりです。
・被相続人の除籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄抄本
・相続人の本人確認書類
・銀行所定の請求書、委任状(代理人が請求する場合)など
司法書士に依頼するメリット
預貯金の解約・払戻しに関する手続を司法書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
〇相続登記を含めた相続手続全体のサポート
預貯金の解約・払戻しに必要な書類のほとんどは、相続登記(不動産の名義変更)に必要なものと共通します。
また、多くの場合、相続財産の中には自宅の不動産が含まれています。
そして、相続による不動産の名義変更については、司法書士が唯一の専門家であるといえます。
つまり、相続登記を司法書士に依頼する際に、預貯金の解約・払戻しもあわせて依頼することで、これらの相続手続をまとめてサポートしてもらうことができるのです。
なお、相続登記については、こちらの記事をご参照ください。
まとめ
預貯金の解約・払戻しは、手続そのものが難解というわけではありませんが、金融機関ごとに必要書類や書式の記入方法、職員の対応などが異なる場合もあり、煩雑と感じやすいのではないでしょうか。
一方で、残された方にとっては、預貯金は重要な生活資金であり、なるべく早く手続を済ませたいことも多いと思われます。
当事務所では、預貯金の解約・払戻しを含めた相続手続全体を、一貫してサポートしています。
川越市周辺で司法書士をお探しの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。